体の動かし方
2022年の秋頃から月1回くらいでボイストレーニングを受けるようになった。
歌をいまさら本気でやりたいからとかそういうんじゃなくて、自分の体の器はほんとうはどういう風に歌えるのかな、というのが知りたくなったからだ。
4年くらい前に、なんかいつの間にか声が出なくなってるな、と気づいた。
15年くらい前は地声の音域がいわゆるE2〜C5くらいだったんだけど、特に高い方の声が出なくなっていた。
コロナ禍に入った頃に、自分の喉の調子が悪くなったかどうかをいち早く知る方法として、毎朝かんたんな発声練習を続けていた時期もあったが、それでは特に改善しなかった。
まあしょうがないのかな、とは思った。もともと正しいトレーニングを受けていたわけでなく無理な発声を続けていたわけだし、それに加えて四十路を回って体は衰えているのだから。どんどん楽しく歌えない体に変質していくのはさみしいことだが、しょうがない。
ただ最近になって、それでは正しいトレーニングを受け無理のない発声をした自分というのは実際どういうものなのかな、というのが気になるようになった。
自分がこういう声を出したいなどのエゴを排除して、自分の体の器は本来どういう声を出せる可能性を持っていたのだろう、それが知りたくなった。
これって音楽的な興味というよりは、どちらかと言えばフィットネスに近いものなのかなと思う。トレーナーについてもらって、体の動かし方を知っていく構図だ。
実際、トレーナーの話からは意外な示唆が得られている気がする。
たとえば最初に言われたのは、「もっと声が出せるはずだ」。
東京に住まって18年、いつの間にか俺は、近所迷惑にならない程度にボソボソやる声が癖になってしまっていたのだ。
月1回、トレーナーに言われるがままに自分の体を操作して大きな声を出すのは、今まで動かしたことのない部分が動いているようで楽しい。
ペンシルロケットで有名な糸川英夫がバレエを始めたのは60歳を過ぎてからだった。
肉体の充実度という観点では、若いときに体の動かし方を学ぶ方がたやすいのは当たり前だろう。
しかし、歳を取ってからあらためて体の動かし方を学ぶことには、また異なった学習効果があるような気がしてならない。どのような機序で体がいちばんうまく動かせるのかという筋道を熟慮することについては、若いときよりも深く理解し楽しめるのではないだろうか。
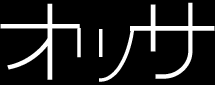



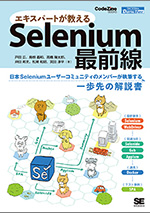

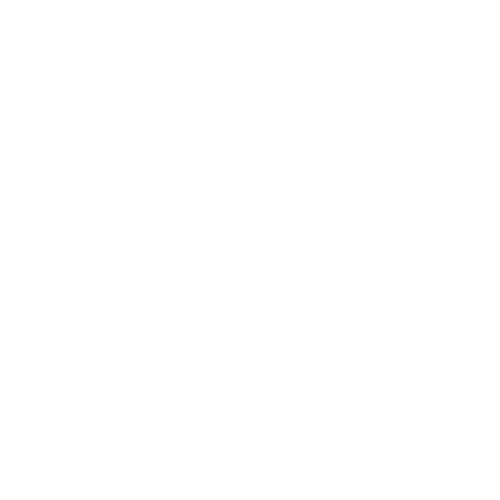 @hiroshitoda
@hiroshitoda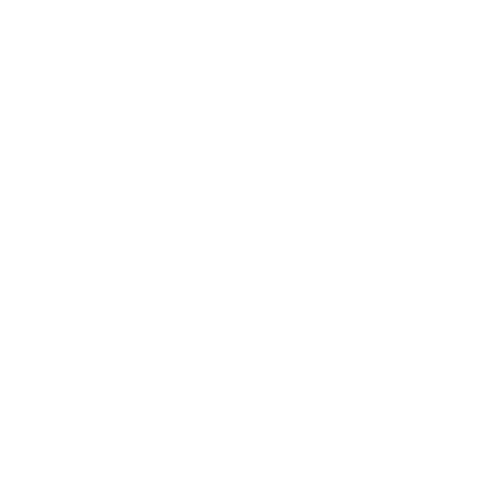 @hiroshitoda
@hiroshitoda @hiroshitoda
@hiroshitoda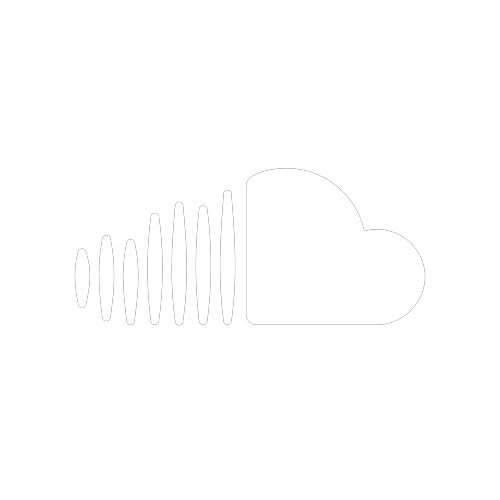 @hiroshitoda
@hiroshitoda @hiroshitoda
@hiroshitoda @hiroshitoda
@hiroshitoda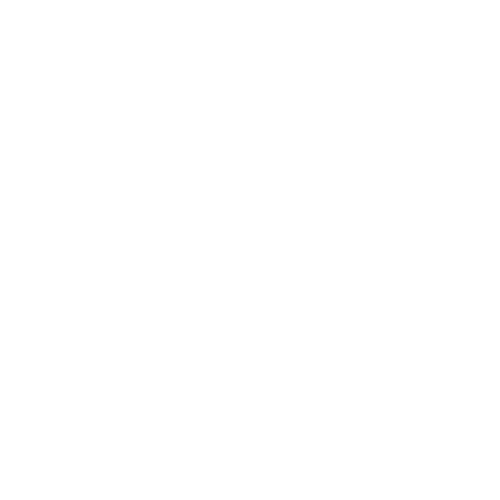 @hiroshitoda.bsky.social
@hiroshitoda.bsky.social